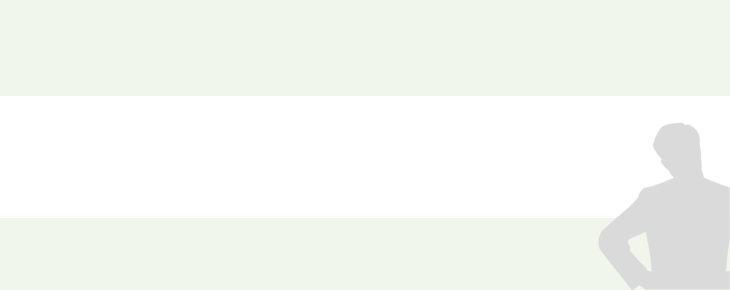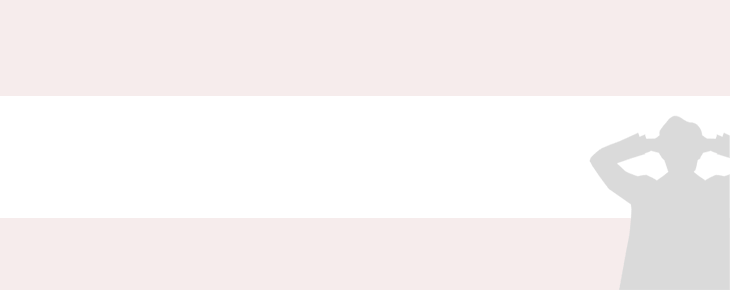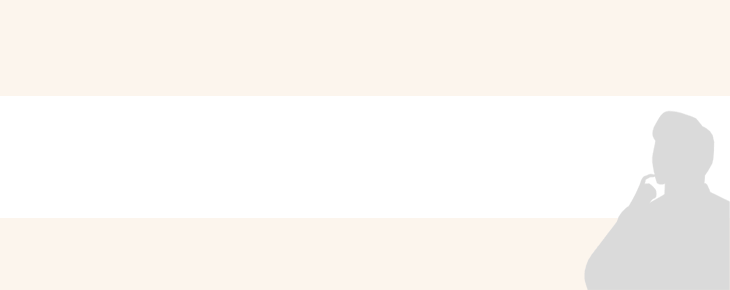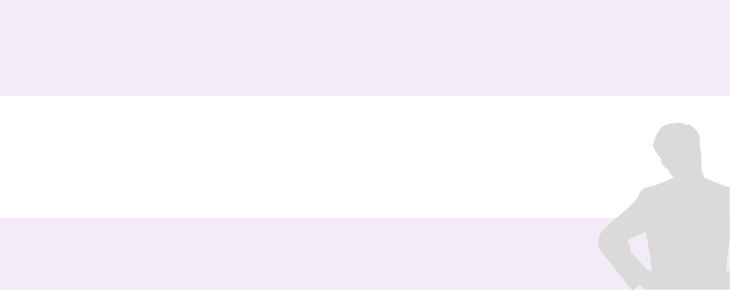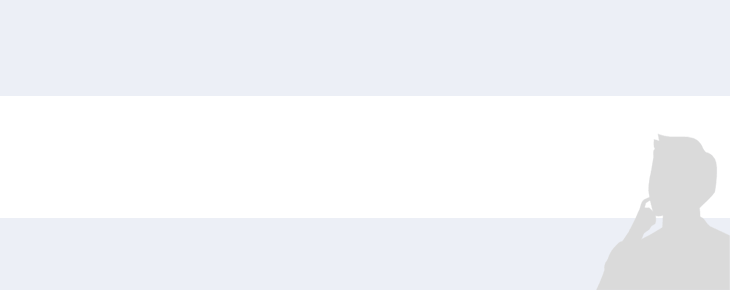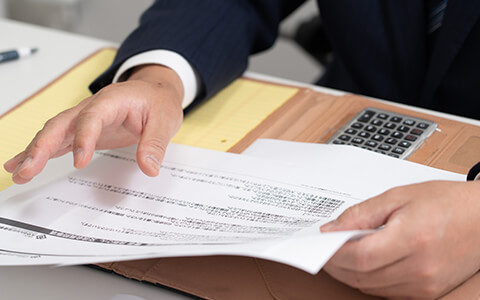遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?
遺言は、遺言者が自由に修正や撤回することができます。具体的には、以下の方法に従う必要がありますので、ご注意ください。
(1)遺言の訂正・加入・削除(以下では、これらを併せて「訂正等」といいます。)について
①自筆証書遺言と秘密証書遺言 これらの遺言の修正は、遺言者自身が、変更箇所を指示し(ex.二重線を引く)、変更したことを付記し、その付記部分に署名をしたうえ、変更箇所に押印が必要となります。この訂正方法に反する方法では、遺言の修正とは不十分であり、変更前の遺言の効力が維持されることになってしまうため、注意が必要です。また、遺言書に文言を加えたり、削除したりしたい場合についても、同様の方法を採る必要があります。もっとも、このような訂正・加入・削除方法を採らなくても、後述の「遺言の撤回方法」を採用した方が、遺言の訂正等が無効となるリスクを減らし、変更したい内容を遺言に確実に反映しやすくなるといえるでしょう。
②公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場にて保管されているため、訂正等を遺言者一人で行うことはできません。基本的には、新たな遺言書を作り直すことになり、その際は、公正証書遺言以外の遺言を作成するのでも構いません(詳しくは、後述の「遺言による撤回」をご参照ください。)。ただし、遺言内容自体を変更せず、表記を変更する程度である場合には、公証人の判断で、「更生証書」や「補充証書」、場合によっては「誤記証明書」を作成してもらうことで、公正証書遺言の訂正等が認められることがあります。
(2)遺言の撤回 遺言の撤回方法は、以下の4つの方法があります。
①遺言による撤回(民法1022条) 遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回できます。その際、撤回対象となる遺言と同じ遺言方式である必要はありません。たとえば、公正証書遺言を撤回しようとする場合、新たに有効な自筆証書遺言を作成し、そこに「前の公正証書遺言を撤回する。」などと記載すれば、遺言の撤回が認められます(新たな遺言の効力が認められます)。
②抵触遺言による撤回(民法1023条1項) ①のように、新たな遺言に撤回する旨の記載がない場合であっても、新たな遺言が前の遺言の内容と抵触(矛盾)するときには、当該抵触部分は撤回されたものとみなされます。
③抵触行為による撤回(民法1023条2項) 遺言の内容と、その後の遺言者の法律行為とが抵触する場合にも、当該抵触部分は撤回されたものとみなされます。たとえば、遺言者Aが、「不動産甲は、Xに遺贈する。」という遺言を作成したものの、その後Aが不動産甲をYに贈与した場合、遺言と遺言者の法律行為が抵触(矛盾)するため、Xへ遺贈する旨の遺言は撤回されたということになります。
④遺言書の破棄による撤回(民法1024条) 遺言者が、既に作成した遺言書や遺贈の目的物を故意に破棄した場合、その破棄部分は撤回されたものとみなされます。たとえば、遺言者Aが「絵画甲は、Xに遺贈する。」という遺言を作成したものの、その後Aがその遺言書をわざと破棄したり、絵画甲を破棄したりした場合には、その遺言は撤回されたということになります。
遺言の訂正等や撤回は、遺言の作成同様、方法が厳格に定まっています。新たに遺言書を作成することで、変更したい内容を含んだ遺言書を有効に作成しやすいですが、それでも有効な遺言書を作成することが必須となります。遺言の作成や訂正、撤回などについて不安や疑問がありましたら、ぜひ専門家にご相談ください。
失敗しない弁護士の選び方
- 弁護士によって結果に差が出るの?
- 弁護士って怖くないの?


詳しくはこちら
相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は60分で無料で対応いたします。
- 新規予約専用
- 0120-367-602
- 事務所
- 097-574-7225

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!
大分みんなの法律事務所の5つの強み
相続アドバイザー資格を有する弁護士による専門性の高いサポート
経験豊富な相続アドバイザー資格を持つ弁護士が在籍しています。豊富な専門知識をもとに、複雑な案件への対応や、様々な事情を考慮したうえでの総合的なサポートが可能です。
専門知識を駆使して、最適な解決を目指します。
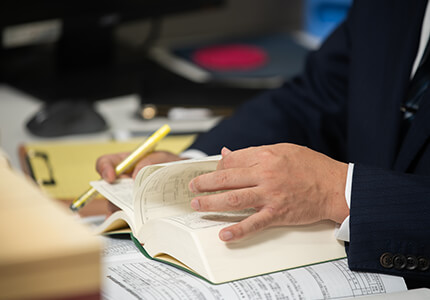
生前対策から紛争案件までトータルサポート
相続の相談は、それぞれ個々が抱える状況が異なります。当事務所の弁護士は相続全般にわたる知識を持ち、それぞれの状況に応じた総合的なアドバイスを提供します。
当事務所では、生前の遺言書作成支援から、相続発生後の相続手続き代行や、調停・裁判の対応までワンストップで依頼が可能です。

わかりやすく丁寧な説明
当事務所では、依頼者の皆様に対して、わかりやすく丁寧な説明を行うことを心掛けています。相続に関する法律や手続きは複雑であり、理解しにくい部分も多いため、専門用語をかみ砕いて説明し、依頼者の皆様が安心して理解・信頼いただけるよう努めています。問題解決の過程で発生する可能性のあるリスクや対策についてもしっかりと説明し、依頼者様の疑問や不安に耳を傾け、納得いただける形で解決を目指します。
.jpg)
親切で丁寧な対応
当事務所では、弁護士だけでなく事務員も含め、全スタッフが一丸となって親切で丁寧な対応を心掛けています。依頼者の皆様が安心してご相談いただけるよう、細やかな気配りと丁寧な説明を行い、常に依頼者の立場に立った対応を実践しています。何かご不明な点やご不安がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
-1.jpg)
初回相談料無料
初回のご相談は無料で承ります。専門家の意見を気軽に聞ける機会を提供し、安心して相続に関するご相談を始められます。相続は、時間との勝負になる案件も多いです。早めの相談が解決への第一歩です。お気軽にご相談ください。

無料相談の流れ

- お電話、メールフォーム
または
LINEで相談予約 - まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

- ご相談・費用の
お見積り - 弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

- ご契約・サポート
開始 - サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。