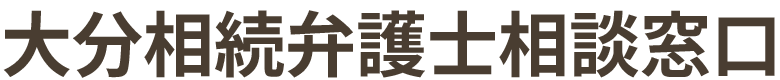後妻の主張を退け法定相続分通りに分配し、相続争いを見事に解決した事例

ご相談者様
依頼者:2名(ご兄弟2名)
相手方:後妻
被相続人との関係:親子
相続財産:自宅不動産(土地・建物)約1,200万円、預貯金約100万円、被相続人が亡くなる直前の預金引き出し約400万円、山林約10万円以下(固定資産税評価額上)
エリア:大分市内(依頼者)、ご実家・相手方(宮崎県)
争点
相談の背景
被相続人が亡くなったあと、後妻から自分が全て相続するといった内容の遺産分割協議書が送り付けられてきました。
ご依頼者の方々は、①法定相続分通りで遺産を分けたい②後妻さんとは関係性が悪かったため、直接話し合いをしたくない というご希望を持っており弁護士に交渉を代わってもらうために当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応
ご依頼者の方は大分市内にお住まいでしたが、被相続人や後妻は宮崎県にお住まいだったため、実際の遺産の内容や評価額が正しいか判断できなかったため、まずは弁護士が遺産を調査するところからスタートしました。
弁護士が遺産を調査しているなかで、当初遺産分割協議書に書いてあった遺産以上の特別受益(被相続人が亡くなる直前に後妻が引き出した預金)約400万円が見つかりました。
そこで、実家不動産と預貯金、特別受益の3点を法定相続分通りに分けるための話し合いをスタートさせました。
まず当職から相手方へ連絡をしたところ、相手方も弁護士に依頼し、相手方弁護士から連絡がありました。
相手方の主張は、下記の3点となり、
①被相続人が亡くなる前の10年間、被相続人が難病だったため自宅で介護していた寄与分
②葬儀費用・墓地・お布施等の費用約300万円
③ご依頼者へ被相続人から約100万円の貸付があったこと
遺産は全て後妻が取得するものといった内容でした。
また、現在住んでいる自宅不動産にも当然住み続けるものという内容でした。
当職としては、法定相続分通りの遺産を分配すること、特に後妻が自宅不動産に住み続けたいならば代償金を支払うように求めました。
交渉を進めていましたが、平行線を辿り解決は望めないと感じたため、早期解決のためにもすぐに遺産分割調停に切り替えることにしました。
調停では双方とも主張などは変えませんでした。
介護の寄与分を訴えるような相手方の主張は、家庭裁判所の調停で認めてもらうには実務上難しいような構成だったため、その点を重点的に指摘し、寄与分を認めさせないようにしました。(専従性のあった介護ではなかったこと)
そうしたところ、相手方は寄与分の主張を諦めました。
また今回ご依頼者の方々はお父様の葬儀にも呼ばれていなかったため、葬儀代に関しても相手方が負担するものだという主張をしたところ、そちらも納得させることができました。
また、被相続人が約100万円を依頼者に貸したといった主張がありましたが、依頼者はそういったことはなかったと主張しており、さらに貸した証拠も無かったため、相手方の主張も取り下げることができました。
結果
結果的に、相手が主張したことを全て取り下げることができ、遺産の全てを法定相続分通りに分ける形で決着させることができました。
結果的に代償金を依頼者お二人が400万円ずつ得ることができました。
担当弁護士のコメント
寄与分の算定は非常に揉める部分ですが、実際判例で明確なルールが示されていません。しかし、実務上の家庭裁判所のルールはあるため、そのルールを当職が利用し、相手方との交渉に生かしました。
そうしたことで、結果的に遺産を希望通りに獲得することができたと思われます。