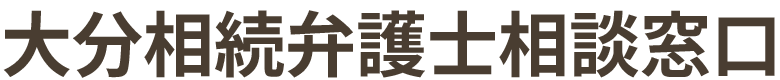遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?
遺言書によって遺産分割の内容が指定されている場合、基本的にその遺言書の内容に従う必要があります。 しかし、例外的に遺言の内容と異なる遺産分割が認められる場合があります。この例外が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。 ①遺言により遺産分割が禁止されていないこと 遺言者は、相続開始から5年を限度に、遺産分割の禁止をすることができます(民法908条1項)。そのため、遺言者が遺産分割を禁止している場合、その期間中、相続人らは遺産分割を行うことができません。 ②相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割について同意していること 遺産分割協議自体、相続人全員が合意が必要となるもの…