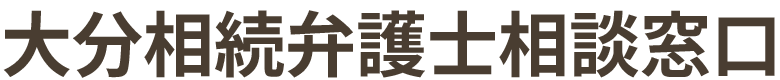葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がするのですか?
誰が葬儀代(葬儀費用)を支払うべきかについて、法律では定められていません。また、葬儀代は、被相続人死亡後に発生した債務であって、被相続人の遺産に含まれないと考えられているため、当然に相続人がその債務を承継することにもなりません。
そこで、一般的には、葬儀の主催者である「喪主」が支払うことが多いようです。もっとも、喪主が支払うということは慣行に過ぎませんので、遺族間での話し合いの中で、「誰が葬儀代を支払うか」や「どのように分担して支払うか」などを決定することもできます。
裁判例においても、原則として喪主の支払義務を認めるものもありますが、他の相続人が葬儀代を負担するような合意があればそれが妥当することになると考えられます。
法律によって誰が葬儀代を負担しなければならないとされていない以上、いざ葬儀代を誰かしら負担しなければならない状況となった場合、相続人間でトラブルに発展する可能性があります。こうした場合、葬儀代だけでなくその後の遺産分割手続きにおいてもそのトラブルが引き継がれ、手続きが上手く進まなくなることも考えられます。こういった状況を回避するためには、可能な限り、事前に相続人間で(場合によっては被相続人となる方も含めて)葬儀代をどのように負担するかを話し合っておくことが重要です。
また、葬儀は被相続人の死後すぐに行われるため、その葬儀代の準備も大変です。しかも、被相続人の預金債権は、基本的に遺産分割の対象となるという最高裁判決があるため、安易に被相続人の預金を引き出すこともできません。そのため、もし相続人のあなたが葬儀代を支払わざるを得ないとなった場合、自己の財産だけでは葬儀代を賄えないことも想定されます。
しかし、民法909条の2は、一定の金額の限度となりますが、相続人が葬式の費用などについて例外的に被相続人の預金を引き出すことを認めています。ここでいう一定の金額とは、大まかにいうと、①預金債権額の3分の1に当該相続人の相続分をかけた金額、②150万円のいずれか低い金額となります。
たとえば、被相続人の息子2人のみが相続人であり、被相続人が1200万円の預金債権を有している場合に、息子1人が葬儀代を預金債権から引き出したいとき・・・
①1200万円(預金債権額)×1/3×1/2(息子の法定相続分)=200万円 と
②150万円を比較すると、②の方が低い金額となるので、息子は150万円の限度で預金を引き出すことができます。