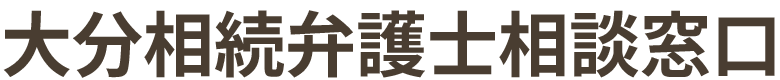相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?
共同相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割手続きに影響が出る可能性があります。遺産分割協議を有効に成立させるには、大前提として、共同相続人全員が判断能力を有しており、その全員が合意していることが必要となります。しかし、認知症の方が十分な判断能力を欠くと判断される場合、(たとえ形式的な遺産分割協議があったとしても、)遺産分割協議が有効に成立しません。
認知症などによって、判断能力を失っている方が法律行為(遺産分割協議)を行うには、代理人を立てる必要がありますが、代理人の立て方としては、①成年後見制度の利用、②があります。それぞれ特徴(メリット・デメリット)がありますので、具体的な状況に応じていずれかを選択しましょう。
①成年後見制度(法定後見)の利用 家庭裁判所が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」と判断した場合、後見開始の審判とともに、成年後見人が選任されます。その成年後見人が、認知症など判断能力を失っている方(「成年被後見人」と呼ばれます。)の法律行為を代わりに行います。後見開始の審判と成年後見人の選任にあたっては、本人や配偶者、4親等以内の親族などが、家庭裁判所に対して、後見開始の審判の申立てを行うことが必要となります。
メリット:後見開始の審判がなされた場合、成年後見人が代わりに遺産分割協議に加わることで協議を進行することができます。また、後述の特別代理人と異なり、成年後見人は、その遺産分割協議に限らず、今後の大半の成年被後見人の法律行為を代わりに行うことができます。そのため、認知症の方が単独では行いえない法律行為を全般的に代わりに行ってあげられることがメリットといえるでしょう。
デメリット:後見開始の審判は家庭裁判所の判断で行われますので、誰が成年後見人に選任されるか分かりません。そして、後見開始の審判が取り消されない限り、選任された成年後見人に対して報酬を支払い続けることになるので、金銭的な負担は大きくなる傾向にあるといえるでしょう。また、仮に成年後見人として、成年被後見人の親族が選任されたとしても、成年後見人と成年被後見人が共同相続人である場合など、利益相反の関係(両者が遺産を分け合う状況にあり、成年後見人が自己の利益を優先する可能性のある関係)にある場合には、成年後見監督人や特別代理人を選任する必要があります。
②特別代理人の選任 家庭裁判所が、遺産分割協議など特定の家事事件についてのみ、成年被後見人の代理人(これを「特別代理人」と呼びます。)を選任することがあります。特別代理人の選任は、利害関係人の申立てがあった場合だけでなく、家庭裁判所が職権で選任することもあります。
メリット:特別代理人は特定の家事事件についてのみ成年被後見人の代理人を務めることになります。そのため、特別代理人に支払うべき報酬もその代理行為の限度となります。
デメリット:逆に特別代理人は、それ以外の成年被後見人の法律行為を代理することはできません。そのため、成年被後見人が法律行為を行おうとする場合、日用品の購入など日常生活に関する法律行為を除き、別途成年後見人の選任が必要となります。
相続人の中に認知症の方がいる場合において、遺産分割協議を有効に成立させるには、上記のいずれかの代理人方法で、代理人を選任する必要があります。いずれの方法を選択すべきかの判断は難しいこともあります。疑問点がありましたら、専門家に相談することをお勧めいたします。