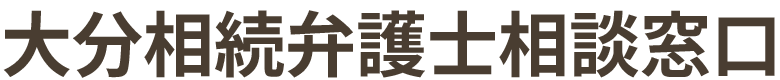複数人で不動産を相続した場合不動産をどう分割すべきか?
(1)遺産分割協議 複数人で不動産を相続した場合、まずは、共同相続人全員で、合意できる分割方法がないか協議しましょう(この協議を「遺産分割協議」といいます。)。
この際、考えられる分割方法としては、以下の4つの方法が考えられます。
①現物分割 共同相続人間で、遺産をそのまま(物理的に)分ける方法をいいます。空き地などであれば、分筆(登記簿上1つの土地を2つ以上に分けること)によって、相続人それぞれが分筆後の土地を単独所有することができるため、現物分割は可能です。しかし、建物については、物理的に分けることが不可能(又は著しく困難)であるため、現物分割をすることはできません。
②代償分割 一部の相続人が不動産を取得し、その代わりとして、取得した相続人が他の相続人に対して、具体的相続分に応じた代償金を支払う方法をいいます。ある相続人(A)は遺産の取得を希望する一方で、他の相続人(B)は取得を望まない場合などには、代償分割を採用することで、AとBそれぞれが希望を叶えることができます。
③換価分割 遺産である不動産を売却し、その売却代金を共同相続人間で分ける方法をいいます。共同相続人間で誰もその不動産の取得を希望していない場合にとても有効な分割方法となります。
④共有分割 遺産である不動産を共同相続人の共有名義とする方法をいいます。相続開始時の遺産共有状態をそのまま引き継ぐことになりますが、共同相続人間で関係が悪化すれば、その不動産を売却するのも、修理したりするのも簡単にはいかなくなります。そのため、可能な限り④共有分割は避けるべきといえるでしょう。
(2)遺産分割調停 遺産分割協議が調わない場合、相続人が申し立てることで、遺産分割調停を行うことができます。調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員の意見を踏まえつつ、共同相続人間で合意できる解決策を模索します。遺産分割協議と異なり、裁判官などの第三者が間に入ることで、遺産分割が成立する可能性があります。もっとも、調停による遺産分割の成立には、共同相続人全員の合意が必要となります。
(3)遺産分割審判 遺産分割調停が成立しなかった場合、自動的に遺産分割審判に進みます。審判まで進んだ場合、最終的に裁判官が決定した分割方法に従うことになりますので、自己の主張が受け入れられるように、的確な主張と適切な証拠を準備する必要があるでしょう。審判の内容に不服がある場合、即時抗告(不服申立て)をすることが可能で、この場合には高等裁判所で審理されます。審判の日から2週間が経過して即時抗告がなければ、その審判で確定します。確定した審判書があれば、遺産である不動産につき単独で登記申請をすることができます。