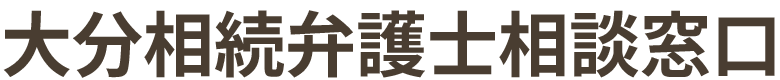夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?
相続人となりうるのは、配偶者・子ども・直系尊属・兄弟姉妹のです。そのため、あなたの夫の妹夫婦は、あなたの相続人には当たりません。そこで、以下の方法を採ることで財産を残すことが可能です。
(1)遺贈 遺贈とは、遺言によって、自らの財産を無償で他人に与えることをいいます。具体的には、遺言書に、「遺言者は、遺言者の有する財産を、夫の妹夫婦に包括して遺贈する。」などと記載することが考えられます。
後述の「生前贈与」と類似している部分がありますが、以下の点で生前贈与と異なります。①遺言者の「遺贈する」という意思表示で足りること(⇒遺贈の受取人とされる者(「受遺者」といいます)の承諾が不要) ②遺贈をいつでも撤回することができること ③遺贈の効果が発生するには、遺言書自体が有効に成立していること
(2)生前贈与 生前贈与とは、贈与者(財産を贈与したいと考えている方)が、生存中に、受贈者(贈与を受ける方)に財産を渡すことをいいます。贈与契約となるので、贈与者と受贈者の意思表示が必要となります。書面は必ずしも必須ではありませんが、書面を作成した場合には、相手方の同意がない限り、贈与契約を解除することはできません。一方で、書面によらない贈与契約の場合には、履行が終わった部分を除き、各当事者が解除することができます(民法550条)。
(3)死因贈与 死因贈与とは、贈与者の死亡を原因として、贈与者から受贈者へ、贈与者の財産を贈与することをいいます。民法上、死因贈与は、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」と規定されており(民法554条)、基本的には遺贈と類似する部分が多いです。
しかし、遺贈と異なる点としては、以下のものが挙げられます。①死因贈与も贈与契約の一種であるため、贈与者・受贈者双方の意思表示が必要であること ②書面による贈与の場合、死因贈与を簡単に解除(撤回)できないこと ③(死因)贈与契約自体、書面は不可欠ではなく、口頭でも成立すること。
それぞれの方法の特徴を見比べつつ、適切な方法を選択しましょう。もし、「どの方法が良いのか分からない」や「こういう手順で合ってるのか」と不安に思うことがありましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
なお、他にも、相続人でない方に財産を渡す方法はあります。ただし、本件のように、被相続人の方が、生存中に、夫の妹夫婦に財産を遺したいと考えている場合には、上記(1)~(3)の方法を採る方が適切であるといえます。そのため、以下では、これらの制度の概要を簡単に紹介するにとどめます(これらの制度の詳細については、【寄与分-2】をご参照ください)。
(4)特別寄与(民法1050条) 特別寄与制度とは、死亡した被相続人のために無償で療養看護その他の労務の提供をした被相続人の親族(この親族を「特別寄与者」といいます。)が、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭(この金銭を「特別寄与料」といいます。)の支払いを求めることができる制度のことをいいます。
もっとも、この制度は相続人がいることが前提となりますし、被相続人の方が生存中に親族の方に財産を残したいと考えているのであれば、上記(1)~(3)の方法を採る方が適切であるといえるでしょう。
(5)特別縁故者への相続財産分与(民法958条の2) 「特別縁故者」とは、相続人が不在の場合に、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。相続人がいるか明らかでない場合、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任し、相続人や相続債権者(被相続人に対して債権を有していた者)がいないか捜索します。相続人がおらず、相続債権者や受遺者に対して弁済をしても相続財産が余る場合には、特別縁故者がその相続財産を得ることができます。
もっとも、被相続人の方が生存中に特別縁故者に該当する方に財産を遺したいと考えているのであれば、上記(1)~(3)の方法を採る方が適切であるといえるでしょう。