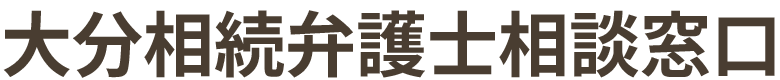遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?
遺言は、遺言者が自由に修正や撤回することができます。具体的には、以下の方法に従う必要がありますので、ご注意ください。
(1)遺言の訂正・加入・削除(以下では、これらを併せて「訂正等」といいます。)について
①自筆証書遺言と秘密証書遺言 これらの遺言の修正は、遺言者自身が、変更箇所を指示し(ex.二重線を引く)、変更したことを付記し、その付記部分に署名をしたうえ、変更箇所に押印が必要となります。この訂正方法に反する方法では、遺言の修正とは不十分であり、変更前の遺言の効力が維持されることになってしまうため、注意が必要です。また、遺言書に文言を加えたり、削除したりしたい場合についても、同様の方法を採る必要があります。もっとも、このような訂正・加入・削除方法を採らなくても、後述の「遺言の撤回方法」を採用した方が、遺言の訂正等が無効となるリスクを減らし、変更したい内容を遺言に確実に反映しやすくなるといえるでしょう。
②公正証書遺言 公正証書遺言は、公証役場にて保管されているため、訂正等を遺言者一人で行うことはできません。基本的には、新たな遺言書を作り直すことになり、その際は、公正証書遺言以外の遺言を作成するのでも構いません(詳しくは、後述の「遺言による撤回」をご参照ください。)。ただし、遺言内容自体を変更せず、表記を変更する程度である場合には、公証人の判断で、「更生証書」や「補充証書」、場合によっては「誤記証明書」を作成してもらうことで、公正証書遺言の訂正等が認められることがあります。
(2)遺言の撤回 遺言の撤回方法は、以下の4つの方法があります。
①遺言による撤回(民法1022条) 遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回できます。その際、撤回対象となる遺言と同じ遺言方式である必要はありません。たとえば、公正証書遺言を撤回しようとする場合、新たに有効な自筆証書遺言を作成し、そこに「前の公正証書遺言を撤回する。」などと記載すれば、遺言の撤回が認められます(新たな遺言の効力が認められます)。
②抵触遺言による撤回(民法1023条1項) ①のように、新たな遺言に撤回する旨の記載がない場合であっても、新たな遺言が前の遺言の内容と抵触(矛盾)するときには、当該抵触部分は撤回されたものとみなされます。
③抵触行為による撤回(民法1023条2項) 遺言の内容と、その後の遺言者の法律行為とが抵触する場合にも、当該抵触部分は撤回されたものとみなされます。たとえば、遺言者Aが、「不動産甲は、Xに遺贈する。」という遺言を作成したものの、その後Aが不動産甲をYに贈与した場合、遺言と遺言者の法律行為が抵触(矛盾)するため、Xへ遺贈する旨の遺言は撤回されたということになります。
④遺言書の破棄による撤回(民法1024条) 遺言者が、既に作成した遺言書や遺贈の目的物を故意に破棄した場合、その破棄部分は撤回されたものとみなされます。たとえば、遺言者Aが「絵画甲は、Xに遺贈する。」という遺言を作成したものの、その後Aがその遺言書をわざと破棄したり、絵画甲を破棄したりした場合には、その遺言は撤回されたということになります。
遺言の訂正等や撤回は、遺言の作成同様、方法が厳格に定まっています。新たに遺言書を作成することで、変更したい内容を含んだ遺言書を有効に作成しやすいですが、それでも有効な遺言書を作成することが必須となります。遺言の作成や訂正、撤回などについて不安や疑問がありましたら、ぜひ専門家にご相談ください。