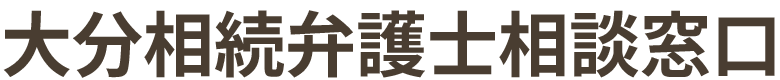遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?
遺言者が死亡し、遺言書が発見された場合、以下のような流れに沿って、遺言を執行していくことになります。
(1)遺言者死亡・遺言書発見~検認までの流れ
この段階については、遺言書の種類によって、それぞれ対応が異なってきます。
ア 保管制度を利用していない自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合 自筆証書遺言・秘密証書遺言を保管している方や、これらの遺言を発見した方は、家庭裁判所に提出し、「検認」を受ける必要があります(民法1004条1項)。この検認は、遺言書の偽造変造や隠匿を防止するために行われます。また、封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人の立会いがなければ、開封してはならないとされています(同条3項)。これらの規定に反した場合、5万円以下の過料が処されることになりますし(民法1005条)、相続人や受遺者の間で遺言の有効性について争われる可能性が高まります。
イ 保管制度を利用した自筆証書遺言の場合 自筆証書遺言保管制度を利用している場合には、その自筆証書遺言は法務局に保管されています。そのため、遺言者が死亡した場合、相続人や受遺者、遺言執行者などは、遺言を保管する法務局に対し、その遺言書の閲覧などを請求することができます。また、この制度を利用した自筆証書遺言については、偽造変造・隠匿のおそれがないため、家庭裁判所による「検認」を受ける必要もありません。
ウ 公正証書遺言の場合 公正証書遺言の場合、遺言は公証役場に保管されており、偽造変造・隠匿のおそれがないため、家庭裁判所による「検認」を受ける必要がありません。
(2)遺言の執行の流れ
遺言の内容のうち、相続分の指定や遺産分割方法の指定などについては、相続開始とともに効力が発生すると考えられます。一方で、遺言内容を実現するにあたっては、「遺言の執行」が必要となる事項もあります。遺言の執行を誰が行うかは、遺言執行者がいるか否かにより変わります。
ア 遺言執行者がいる場合 遺言執行者が、遺言内容を実現するために、遺言の執行に必要な一切の行為を行うことになります(民法1012条1項)。たとえば、①遺言執行者がいれば、「遺贈の履行(ex.遺産の引渡しや登記移転など)」は遺言執行者のみが行うことができるとされています(同条2項)。また、②遺産に属する財産を特定の共同相続人に承継させる遺言(このような遺言は、「特定財産承継遺言」と呼ばれています。)がある場合には、遺言執行者が行うことができる事項が多いです。具体的には、遺言執行者が、その共同相続人が対抗要件を具備させるために必要な行為をしたり(同法1014条2項)、特定財産承継遺言の対象が預貯金債権である場合には、その預貯金の解約などを申し入れたりすることができます(同条3項)。
遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産の処分その他の遺言執行を妨げる行為をすることはできず(同法1013条1項)、相続人がそのような行為は無効となります(同条2項本文)。
イ 遺言執行者がいない場合 遺言執行者がいない以上、遺言の履行(遺言内容の実現)は、相続人が行うことになります。たとえば、遺言に「遺言者は、その有する甲土地を、A(相続人以外の者)に遺贈する。」という内容が含まれている場合、相続人は、相続人でないAに対して、遺贈を履行する義務を負うことになります。