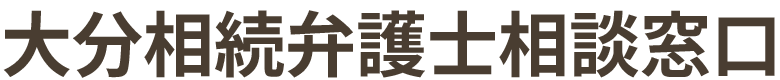被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?
民法は、相続放棄を行うには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があると規定しています。そのため、相続放棄を希望する相続人が①被相続人が死亡したこと、②自己が相続人に当たることを認識した場合には、「自己のために相続の開始があったことを知った」として、そこから3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります(この期間を「熟慮期間」といいます)。熟慮期間を過ぎた場合、基本的には相続放棄をすることはできず、単純承認をしたものとみなされます。
しかし、最高裁の判例(昭和59年4月27日)は、例外的に熟慮期間を延ばすことが認められる場合があると示しました。ただし、その判例の事案には特殊な事情があったことには注意する必要があります。具体的には、被相続人と相続人との間の交流が途絶えており、相続人が被相続人の死亡を知ってからも限定承認や相続放棄をすることなく1年が経過したところ、被相続人の連帯保証債務(消極財産)が見つかったという事案でした。
この事案につき、最高裁は、「相続人が…(相続の開始と自らが相続人となったこと)を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信じるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである」と判断しました。これは、熟慮期間自体を延長するものではありませんが、熟慮期間の起算点(開始時期)を遅らせることで、相続人が相続放棄(又は限定承認)を行う機会を確保しようとする判断といえるでしょう。
ただし、上記の判決は、「熟慮期間の起算点を遅らせることが許容されるための要件」として、大きく分けて以下の2点を挙げています。
①相続人が、相続開始の事実や自ら相続人となったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったことが、被相続人に相続財産が全くないと信じたことためであること。
②相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるため、そのように信じることについて相当な理由があること。
そのため、たとえば、被相続人が死亡し、同居していた相続人が単に相続財産の有無の調査を怠っていた結果、死亡から1年後に被相続人の連帯保証債務が発覚したような事案であれば、少なくとも②の相当な理由があるとはいえず、熟慮期間の起算点を遅らせることは認められないと考えられます。
「被相続人の死亡から時間が経過した後に消極財産が見つかり、やはり相続放棄をしたい」と考える相続人の方もいらっしゃるかと思います。しかし、判例上、熟慮期間の起算点を遅らせることは簡単に認められません。また、熟慮期間の起算点を遅らせるための①②の要件を満たすことを立証することは簡単ではありません。そのため、もし被相続人死亡から3か月経過後に相続放棄をしたいと思っている方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。