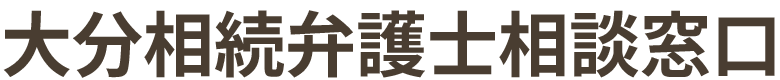相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。
民法の定める「寄与分」の制度は、相続人であることを前提としています。そのため、相続人でない場合には、寄与分の主張をすることはできません。なお、寄与分については、【寄与分-2】をご参照ください。
もっとも、相続人に該当しない場合でも、寄与分の制度に代わるものとして、①「特別寄与料の請求」や②「特別縁故者に対する相続財産の分与の制度」があります。これらの制度が利用できる場合には、「被相続人の療養看護に努めたことなど」を金銭的に評価してもらえることになります。
(1)①特別寄与料の請求(民法1050条)
特別寄与料の請求とは、死亡した被相続人のために無償で療養看護その他の労務の提供をした被相続人の親族(この親族を「特別寄与者」といいます。)が、相続人に対して、寄与に応じた額の金銭(この金銭を「特別寄与料」)の支払いを求めることができる制度のことをいいます。
特徴としては、まず、請求者が「相続人でない親族」であることが要求されるため、被相続人の親族でなければこの対象となりません。また、相続人でない親族が、相続人に対して、金銭の支払いを求めることができるという金銭債権であることも特徴であるといえます。さらに、特別寄与料の請求には、特別寄与者が相続開始と相続人を知った時から6か月、又は、相続開始から1年を経過することで、権利を行使できなくなります。もし、あなたが相続人に該当しない場合でも、特別寄与料の請求ができるのではないかと疑問に思った場合には、ぜひ一度お早めに弁護士へご相談ください。
(2)②特別縁故者に対する相続財産の分与(958条の2)
特別縁故者に対する相続財産の分与制度とは、相続人がいない場合に、「特別縁故者」に、清算後も残る財産の全部または一部を分与する制度をいいます。
被相続人が死亡したものの、相続人がいるか明らかでない場合、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任し、相続人や、被相続人に対して債権を有していた者(「相続債権者」といいます。)がいないかを捜索します。相続人がおらず、相続債権者や受遺者に対して弁済しても相続財産が余る場合には、「特別縁故者」がその相続財産を得ることができます。
「特別縁故者」とは、相続人が不在の場合に、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。①特別寄与料の請求が認められるものが「相続人でない親族」に限定されていたのに対し、②「特別縁故者」は親族に限定されないため、内縁の配偶者なども対象となります。ただし、この制度は、「相続人がいないこと」が大前提となります。捜索中に相続人が見つかった場合には、特別縁故者に相続財産が分与されることはありませんので、注意が必要です。